|
|

|
|
|
| 「電動車いす」は、これまで身体障害者を中心とした移動手段として利用されてきましたが、最近は歩行に困難を感じる高齢者の社会参加手段としても普及してきています。出荷台数も年間約3万台のぺースで増加しており、今後ますますの普及が見込まれます。一方、それにともなって、「電動車いす」に係わる交通事故も増加しています。(財)交通事故分析センターのまとめによると、電動車いす利用者の交通事故死傷者数は、平成2年中に36人だったものが、平成15年には254人と、年々増加傾向にあります。(図1)事故の多くは乗用車などの車両との接触ですので、今後ドライバー側からの安全対策が強く求められてくると考えられます。 | 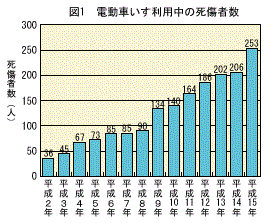 |
|
|
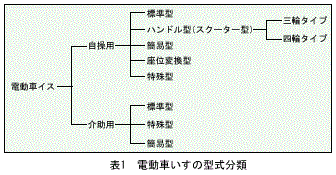 |
|
|
|
| 道路交通法において、「電動車いす」は「身体障害者用の車いす」に含まれ(第2条第1項第11号の3)、「歩行者とみなす」と規定されています。(第2条第3項第1号) このようにみなし歩行者となりますが、歩行者とちがう特徴があります。 |
|
|
| ||||
| |||||||||
| 今後、高齢者人口の増加に伴って、「電動車いす」の利用者が増加するものと予測されます。「電動車いす」は利用者や構造上の特徴から、周囲の状況に的確に対応して危険を自ら回避していくということが著しく困難です。 ドライバーの皆さんは、「電動車いす」の事故防止のため、幼児や高齢者に対するときと同様の思いやりのある態度で、特に次の点に十分注意する必要があります。 | |||||||||
|